紙をめぐる話|紙について話そう。 No.13
|
デジタル以前とデジタル以後。
異なる時代にデザインをはじめた
二人のクリエイターが語り合います。
それぞれが考える紙の未来には、
意外にも多くの接点がありました。
2013年5月17日
初出:PAPER'S No.44 2013 夏号
※内容は初出時のまま掲載しています

| 八木 | 僕は普段コンピュータをいっさい使いません。メールもしない。朝起きたらまず使うのが紙。一日が紙から始まるんです。メモを取るにしても、紙ならパッと開けばすぐに使えるでしょう。名刺だってサッと出せる。起動時間やバッテリーの充電も必要なくて。 |
| 橋詰 | 確かに、テクノロジーが発達している時代だからこそ逆に紙の重要性が高まっている気がします。例えばウェブサイトのディレクションを依頼される時にも、よく聞いてみるとそれを本の形で伝えた方がシンプルで分かりやすいと思うことが多いですよね。 |
| 八木 | 何もかもがコンピュータ化している今は、現物を見る機会がとても少なくなってしまいました。仕事でもそう。アメリカのプレゼンテーションはだいたい20分くらいで自分たちの考え方やデザインを提案するんですが、ほとんどの会社はラップトップで見せている。でも僕らは必ず現物を持っていきます。現物ならクライアントに「こんなに硬いんだ、こんな風に柔らかいんだ」と肌で感じてもらえるでしょう。それが本当のビジュアルコミュニケーションだと思うんですよ。 |
| 橋詰 | 紙からデジタルへ媒体の主軸が移行しつつある中で、人と人をつなげる新しい仕組みが次々と生まれてきていますが「あまりにもすべてがコンピュータの中で語られすぎていないか?」と感じることもあります。紙から得ることのできていた、日常の中にある繊細な皮膚感覚のようなものが消えつつあるんじゃないかと。 |

集めたくなる紙、残したくなる紙。
| 八木 | 紙独特の感覚と言えば、1984年にエスプリという会社に招かれてサンフランシスコに行ったとき、最初に興味を持ったのが現地にある「汚い印刷」でした。ツインタワーやエンパイアステートビルディングの入場チケット、月の地図、紙袋、爪楊枝入れなど、日常周辺にある印刷物が面白くて大量に集めていました。どれも今でも手元に残してありますが、それは紙だからというだけではなくて、紙に印刷がされているからなんですね。何かの痕跡があるから捨てることができなくなるというか。 |
| 橋詰 | 確かにそうかもしれません。ただ同時に僕は、紙が意匠から離れたときに伝わるものもあるって考えているんです。様々な種類の束見本を250点くらい集めた「紙と束見本」展を竹尾さんと開催したのですが、束見本という何も印刷されていないものだからこそ表出する紙そのものの魅力や意味のようなものがあるような気がしていて。特に束見本は、文字通り紙の束ですから、紙が集積することによってできる立体構造、つまり紙の建築としての面白さが出せるのではないかと。この展覧会は意外にもグラフィックデザイナーではない人たちから好評で、デザインという世界を超えて、紙に対する何か新しい視点が生まれてくるのではないかと期待しています。 |
| 八木 | 僕自身は、紙だけだったら手元に残さなかったと思います。やっぱりそこに何かが書かれていることが大切だから。 |
| 橋詰 | そういうことでいうと、「紙と束見本」展を見ていて面白いのは、そこに何も書かれていないことが分かっていながら来場者がみんな束見本をじっと読んでいることです。束見本のかたちから「これは絵本だろうな」「これは雑誌だろうな」と、これからそこに記載されていくものの可能性を想像しているんですよ。だからある意味では束見本も何かが書かれている紙であると言えるのかもしれません。 |
| 八木 | それは面白いですね。印刷もそうですが、特に残したくなるのは手書きのものですね。たとえば石岡瑛子さんの手書き原稿や、田中一光さんの手紙がそうです。 |
| 橋詰 | 確かに手書きには個人のキャラクターが色濃く出ますから、どうしたって捨てられないですね。 |
| 八木 | レシートでもなんでも、今は全部がコンピュータのプリントでしょう。紙すら使わないこともある。十年くらい前まではみんな直筆で、しかもきちんと紙に書いていた。だから手元にずっと置いておきたくなるんです。7月の「紙とグラフィックデザイン─八木保の選択眼」展では、過去の作品の現物に加えて、これまで集めた印刷物も展示しようと考えています。 |

ひとつひとつ、手づくりで。
| 八木 | コンピュータで均一につくられたものってつまらないですからね。手づくりだから新鮮さが感じられるわけで。最近の若い人たちなんかも、手触りのあるものや古いもの、一色刷りが好きだっていう人が増えているでしょう。感覚が昔に戻ってきているんですよ。もちろんピカピカなものにはピカピカならではの良さがあって、それを何と組み合わせるのかが今の時代には大事なんだと思います。 |
| 橋詰 | 紙の使われ方って時代によってどんどん変化しますよね。書店「ユトレヒト」店主の江口宏志さんの本『ハンドブック』(2013年、学研教育出版刊)では、更紙や光沢紙など13種類の用紙を使用しました。表情が異なるさまざまな紙をコンテキストに合わせて使用することで何か新しい価値が生まれるんじゃないかって考えたんです。 |
| 八木 | 倉俣史朗さんが寝る前に書いたメモがたくさん残されていて、それらを一冊の本にまとめたいという依頼を受けたことがありました。印刷費がほとんどない仕事でしたが、どうしても100ページは欲しいと言うので、ゼロックスコピーで本をつくったんです。一枚一枚コピーを取って、それを手作業で二つに折って。印刷や製本の質は高いとは言えませんが、だからこそ魅力的ということもあるんですよ。曲がったキュウリがお店で売れないのとは違って、傷ついたり汚れたりした紙が使えないなんてことはなくて、やり方次第でそこには独特の魅力が生まれる。紙というのはそのくらい自由で多様な使い方ができるし、これからの時代はそんな考え方が当たり前になっていくはずです。 |
| 橋詰 | 確かにこれまでは安い紙は安いコンテンツに使うといったセオリーがありましたが、最近は徐々に崩れてきていますよね。安い紙に箔を押して高級感を出してみるとか、名刺に使ってみるとか、紙の価値の再編集や試行錯誤がすごく起きてきている時代だと思います。 |
| 八木 | 大切なのは、とにかくひとつひとつ手でつくること。最近のグラフィックデザイナーのようにコンピュータの前で版下づくりばかりやっていては、新しいものや魅力的なものは生まれないんです。 |
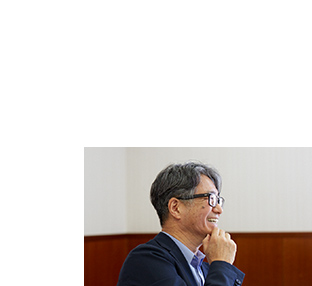
「なんとなくこの色」でいい。
| 八木 | 僕が働いていたエスプリという会社は紙を大量に使う会社として有名でした。メールオーダーのカタログサイズが通常のものに比べてかなり大きくて、毎回のカタログにかける費用も莫大。紙の選択や印刷方法も、カタログを発行する一年以上も前から議論していました。そういう環境にいたので、自然と僕も紙と深く関わることになっていったんです。エスプリのオーナーは環境保護に非常に関心がある方で、80年代後半にはカタログやステーショナリー類のほぼすべてをリサイクルペーパーと植物性インキで印刷していたんですよ。 |
| 橋詰 | 80年代というと、まだ世間では今ほど環境問題に意識が向いていなかった頃ですよね。 |
| 八木 | そうです。今でいうエコの活動にとても早い時期から取り組んでいました。特に画期的だったのが、コーポレートカラーを持つのをやめたことでした。基調色はグリーンでしたが「このグリーンでなければいけない」という決まりをつくらなかったんです。というのも、ヨーロッパやアジアなど、世界中にあるエスプリのツール類にグリーンを載せたとき、リサイクルペーパーではどうしても色が同じにならないから。厳密な色指定をしてその色に合わせようとすると、膨大な費用と資源を費やすことになってしまうんです。 |
| 橋詰 | それでは逆に環境保全というアイデンティティが保てないですね。 |
| 八木 | はい。だからリサイクルペーパーに色を載せる際のルールを「なんとなくグリーンでいい」という緩やかなものにしたんです。インキもできる限り薄く塗って、紙の地肌を出すことをアイデンティティにしました。通常、CIという言葉は「コーポレートアイデンティティ」と解釈されますが、エスプリでは「コーポレートイメージ」と呼んでいたんです。 |
| 橋詰 | 20年以上前のことなのに、いま聞いても新しく感じるお話ですね。実は僕がイギリスのロイヤル・カレッジ・オブ・アート(RCA)に留学したのも、コーポレートアイデンティティをつくること、つまりひとつの芯をつくって求心力を強めるようなことがデザインの役割だっていう日本の風潮に対して疑問を持っていたことが理由のひとつだったんです。エスプリのようにアイデンティティを決めず、紙や色、触感など様々な要素で総合的にサブジェクトを伝える方法もあると思うんです。 |

最後は、紙にかえってくる。
| 八木 | 僕の今の名刺は竹尾さんの紙(ファーストヴィンテージ)を使っています。点字が打ってあるんですが、目の見えない方がこの名刺を手にするとまず紙の触感に注意がいくんですよ。 |
| 橋詰 | 点字よりも先に、ですか? |
| 八木 | そう。点字よりも紙がいいと言うんです。普通は点字さえ打ってしまえばそれでいいと考えがちですが、人間の感覚はそんなに簡単なものじゃない。ものをデザインするためにはそこまでの意識が必要になってくるし、紙にはそれを伝えるための力があるんですね。 |
| 橋詰 | 紙選びの大切さが分かりますね。以前、山口情報芸術センター(YCAM)で行われる子ども向けのワークショップをまとめるためのファイリングシステムをつくったことがありました。そのときは紙の持つフィジカルな魅力を伝えたいという思いから、厚みのある紙を使ったり、折り紙の大きさを喚起させるサイズにしてみたり、RGBには出せない特色のビビッドな世界を表現してみたり、様々なことにチャレンジしたんです。とにかく紙の持つ触感や色を直に感じてほしくて。 |
| 八木 | その紙にしか出せない触感や色ってありますからね。イッセイミヤケさんの本では竹尾の「MTA+ -FS」を使ったのですが、手に持ったときの重みやシャキっとした触り心地は、この紙でなければ実現できませんでした。しかもこの紙、発色がものすごく良くて。どこにでもあるコンパクトカメラで撮った写真が、とてもきれいな色で表現されるんですよ。 |
| 橋詰 | 本当だ、とてもコンパクトカメラで撮ったようには見えませんね…これも紙の力ですね。それを考えると、自由だといわれているコンピュータって実はとても不自由なのかもしれません。金色や銀色も再現できないし、重さも伝わらない。インフォメーションは伝わるかもしれませんが、心の底から「いいね、楽しいね」と思える部分がうまくコミュニケーションできませんから。 |
| 八木 | 結局のところ、最後は紙に戻ってくると思いますよ。紙は土に還りますからね。グラフィックに限らず、ペットボトルに代わる紙のパッケージができていたり、子どもにプラスチックを噛ませないための紙のストローが開発されていたりして、今、紙ってとても元気なんですよ。 |

