紙をめぐる話|紙について話そう。 No.33
|
長くあるから生み出せる新しさ。
余地があるから膨らむ想像力。
どれだけ技術が進んでも、いや、
進むがゆえに、欠かせない存在になる。
紙の価値を改めて
信じさせてくれる対談です。
2021年8月31日
初出:PAPER'S No.64 2021 秋号
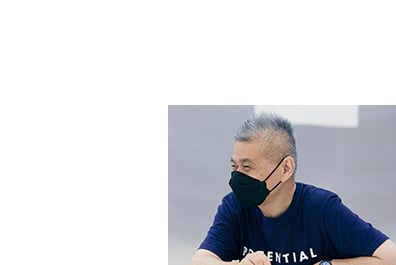
| 津田 | 今日は糸井さんに可愛い紙を持ってきたんです。愛媛でよく作られている「でんぐり紙」のおもちゃなんですが、閉じてある紙をぐるっと360度開くと、飛び出す絵本のようにふくらんでソフトクリームの形になるんです。ここを開くと… |
| 糸井 | わ、本当だ。すごい、何でも持ってますね。さすが『デザインのひきだし』(笑)。 |
| 津田 | ありがとうございます(笑)。でも、それこそ『デザインのひきだし』の取材で色々な場所に行くと、日本中に紙の産地があって、昔から生活の中に紙が根付いていたんだなと思うことが多いんですよね。このおもちゃもそうですし、紙で作られた法被や裃を見せてもらうこともあったりして。 |
| 糸井 | そういえば僕も、初めて自分用に作った着物は紙ですよ。紙を糸のようにしたものを織って作る紙布の着物です。紙も木綿も元をたどれば植物の繊維なわけで、紙は服にだってなるんですよね。 |
| 津田 | 最近、江戸の紙細工を紹介する本を買ったんですが、子どもが遊ぶような姉様人形や、ちょっとした小箱みたいな可愛らしいものが載ってるんだろうと期待してページを開いてみたら、いきなり出てきたのが戦で使えそうなほど立派な兜で。竹で形を編んで紙を貼っていく張り子みたいなものなんですが、すごく丈夫で強そうな見た目をしているんです。確かに昔はプラスチックや樹脂なんてないわけですから、今よりももっと紙が暮らしの中で立体的に使われていたんですよね。提灯や番傘なんかもそうですし、みんな紙だったんだなと。 |
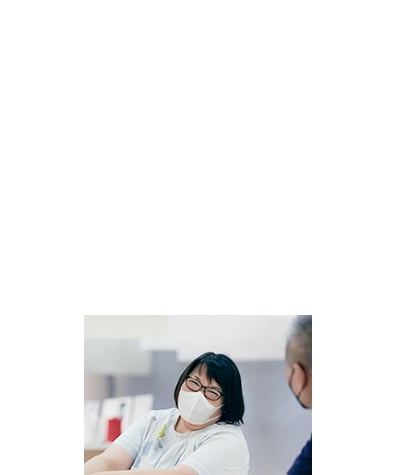
守るという前進。
| 糸井 | 襖に障子に屏風に、そもそも家の中からして紙に囲まれていますしね。思えば、破いたり倒したりなんかして、ふとした拍子に子どもが壊せちゃうような家に住んでいたというのもすごいですよね。危ういところで間違いを犯しながら、直して暮らしていたという。 |
| 津田 | そのときに、わりと安価で誰にでも扱いやすい紙はちょうどよかったのかもしれないですね。『どんな草でも紙になる』という私の大好きな本があるんですが、たとえばたんぽぽでもキャベツでも玉ねぎでも、本当にどんな植物でも、繊維を漉いてシート状にすれば紙になるんです。もともとはそうやって身近にある綿や麻、竹なんかを使って紙を作っていたのかもしれません。 |
| 糸井 | このところよく思うんですが、そういう紙の文化のような「昔からあるもの」の上に、何か次のものを作っていく時代になってきているなと。どうしてパリに観光客が行くかといったら、リノベーションしながら残してきた街並みのような、今から作ろうとしても作れないものがそこにあるからですし。昨年末にほぼ日が竹尾さんの見本帖本店の隣、ここ神田に引っ越してきたのも、まっさらな土地で新しいことをしたいわけではなくて、昔から残っているもの、続いているものがここにはたくさんあるからなんですよね。そこに混ぜてもらったり、受け継いだり、何かを変えていったりすることが今とても面白いんです。で、紙の話もまさしくそうですよね。アナログとデジタル。手書きとタイピング。津田さんも時には「デザインのひきだし、デジタル化しないんですか?」とか「これからは紙よりもWebですよ」といったことを言われることもあるかもしれませんが、 長く続いてきたものを保ち、守ることと、新しく前に進むことは対立概念じゃないんじゃないの?って思うんです。形あるものや古くからあるものを認めたり許したりすることの中に、次が生まれるはずで。そう考えると紙の文化は、昔から続いているものだからこそ生み出せる、何か新しい可能性があるんじゃないのかなって。 |
| 津田 | そうですね。紙だけがいい、デジタルだけが素晴らしい、ではなくてどちらにも良さがあるし、両方を使い分けるのも楽しいですよね。普段、紙の本だけではなくて電子書籍もよく読むんですが、それを言うととても驚かれるんです。「あんなに紙が好きだって言ってたのに、裏切り者―!」みたいな(笑)。そんな、ゼロかイチかっていうことではないじゃないですか。私は旅行が好きでよく離島に行くんですが、電子書籍だとそんな場所でも漫画の続きが買えるのがすごくうれしくて。もちろん家でゆっくり読むときには、本棚に大事に置いてあるお気に入りの本を手にとったりもしますし。 |
| 糸井 | 自然なことですよね。デジタルだけでいいんだったら、それこそ自分の体を使ってやるオリンピックだって、大変だからロボットにさせようとか、いっそデータに競わせればいいじゃんっていうことになってしまうわけで。 |
白い紙が書かせてくれる。
| 津田 | 糸井さんと紙といえば、やっぱり「ほぼ日手帳」がありますが、手帳に使われている「トモエリバー」がすごく有名になりましたよね。糸井さんは普段、何かお書きになる際は手帳を使われたりしますか? |
| 糸井 | ほぼ日の仕事をする中で、必要に応じてコピーを書くことが今でもたまにあって、手帳も含めて白い紙はやっぱりものすごく助かりますね。紙に書いていると、横に置いた文字を見ながら、起承転結を気にせずに考えを漂わせられるのがいいんです。「ほぼ日の學校」を始めるにあたって「2歳から200歳までの。」というコピーを書いたんですけど、仮に、まず「2歳から100歳までの。」っていうコピーを書いたとしますよね。そしたらその文字を眺めながら、紙の上で考えていくんです。たとえば音の世界では、人には聞こえない領域まで音が鳴っているからこそ、聞こえる音が豊かになる…みたいなことがあるわけだから、ここは100歳を飛び越えて200歳って書いたほうがいいんじゃない?なんて、ありえないようなところまで広げていけたりする。白い紙に書いていると、そうやって思いもよらないダイナミックレンジの外側が見えてくるというか。デジタルだと、書いたものの横に別の言葉を置いたり、大きくしたり小さくしたりっていう操作がすごく面倒で。そんなことをしているうちにもう、逃げていってしまうものがあるんですよね。 |
| 津田 | 私も『デザインのひきだし』を編集するときには、調べていることや分からないことをA3くらいの大きな紙につらつらつらつら書き出していきます。たとえば和紙についての特集をするときだったら、「この土地は紙漉きが盛んで、こんな紙を作っていたな」とか「これは知らない部分だからもっと取材に行かなきゃ」といったように、関連することを変な形に伸びていく樹形図のようにしてずーっとつらつら書いていくんです。それは毎回していることで、自分の机のモニターの前に、そのための紙がたくさん置いてあります。書こうと思って書いているというよりは、それを一回大きく広げないと、自分の中でまとまらなくて。 |
| 糸井 | 地図みたいな感じですね。 |
| 津田 | そうなんです。ずーっとつらつら書いているうちに、その地図が思わぬ方に伸びたりすると紙が足りなくなって、しょうがないからまた別の紙をつなげて(笑)。今回はこんな方向へ広がったなあ、なんて思いながら。 |
| 糸井 | いいですねえ。そうやって手を動かして書くことって、ひとつの運動なんですよね。自分の体を使ってする行為ですから、踊りと同じようにその人の固有の体と頭の動かし方があるし、続けていくと知らず知らずのうちに育ってくるものがあるんです。紙の上に文字を書くという行為が、自分の考えを作ってくれるというか。キーボードを打つのは運動として少し単純すぎて、あれはどちらかというと目の仕事なんですよね。 |
| 津田 | 取材などでも感じますが、ノートに書く方が圧倒的に速くて便利ですし、手書きとキーボードでは頭と言葉の連動具合が全然違いますよね。 |
| 糸井 | 手書きって、実はすごいんですよ。白い紙の上に何かを書くことは、どんな時代になってもなくならないんじゃないかなと思いますね。 |

こぼれ落ちたものを拾うと。
| 糸井 | デジタルのようにロジックで組み立てて、合理的なものを良しとするのが今の文明だとすると、理屈から外れて偶然生まれる面白さ、みたいなものの存在感が小さくなってしまいそうですよね。そういうものの良さを忘れたくないなと思ったときに、たとえば写真って、こぼれ落ちるものが写るのがいいんです。意味の重要度や関連度とは違うところで、「こんなものが写っちゃった!」という喜びがあって。 |
| 津田 | 意図せずして写り込むものの面白さで言うと、私、すごく好きなのは紙の裏面なんです。ボール紙などがそうですが、パッケージに使う紙って、当然、目に見える表面のことを最優先に考えて作られていて。そういう紙の裏面の、油断してるような感じがすごく好きなんですね。裏をよく見てみると、毎回微妙に違う発見があるんです。「今回はちょっと濃い色をしているな」とか、「今回はこんなものが混じってるぞ」という、作為的じゃないところがすごく可愛いくて。 |
| 糸井 | 和紙は特に裏面がいいですよね。ざらっとしてたり、でこぼこしてたり。 |
| 津田 | そうなんですよ。デザイナーの中にも、裏面の面白さに気づいてわざとそっちをパッケージの表に持ってきているような人もいて。そういうのを見ると、仲良くなれそう!と思ったりします(笑)。製紙会社の方がそれを見たら、「ええ!これ、間違ってるよ!」って仰ると思うんですけど。 |
| 糸井 | 背中の写真ですよね。 |
| 津田 | そうですね。均一だったり平滑だったり、そういう綺麗な紙ももちろんいいんですが、なんだかざらざらしていて、いつも微妙に違っていて、油断してるような感じ。その隙がいいなって思いますね。写真でいう「写っちゃった!」のような、こぼれ落ちるものが表れる場所が、紙の場合は裏面にあるなあと。こんなことを言われても竹尾さんは困ってしまうと思うのですが。 |
| 糸井 | 竹尾さんの竹という字は紙になるね。尾もなりそうですよね。狐の毛とか漉き込んで。 |
| 津田 | ああー、竹のパルプに尾っぽの繊維を混ぜちゃえばいいんだ。 |
| 糸井 | 竹尾紙。 |
| 津田 | いいじゃないですか!竹尾さん、ぜひ! |
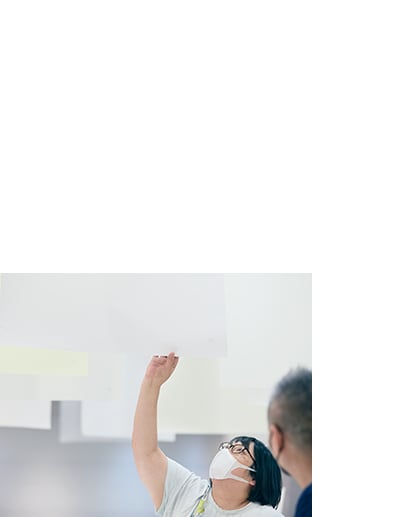
サンタさんがくれたコピー用紙。
| 糸井 | 白い紙に書くことの一方で、印刷された紙というものも、ある力を持っていますよね。中学生のときに、週刊マンガ雑誌で「君も名刺を作らないか」っていう応募企画があったんです。そこで僕は「植木等」という名刺を作って、「こういうものです」と言ってクラスの子に配っていました(笑)。紙に活字が刷ってあることのオフィシャルな感じに、漠然とした憧れがあったんじゃないかな。社会性みたいなものの証拠というか。紙に対する意識が初めて芽生えたのは、僕の場合はまず名刺でしたね。 |
| 津田 | 私は小学生くらいの頃、お気に入りのキャラクターが印刷されているポケットティッシュが大好きでした。当時は毎月のお小遣いが学年×100円だったんですけど、そのポケットティッシュは1個で50円くらいするんですね。1年生のときは100円しか使えるお金がないので、とても貴重なもので。友達同士で違うキャラクターのものを買って、中に入っているティッシュを交換したり。今でこそコピー用紙みたいな、何も書かれていない紙の良さもわかるんですが、当時はそういうものに夢中で。 |
| 糸井 | 白い紙の価値って、普通、子どもにはないんですよね。そこに何が載っているか。つまり紙の上にあるコンテンツ自体に興味を持つわけなので。それにしてもコピー用紙って、舐められていると思いませんか。アイツ、思ったよりずっといいヤツなのに…。 |
| 津田 | そうなんですよ! インクの吸い込み具合もちょうどいいし。ちなみに糸井さん、コピー用紙って何からできているかご存知ですか? |
| 糸井 | えーっと、何だろう…。意外と植物じゃないとか?壁?(笑) |
| 津田 | あれはユーカリやアカシアといった木が原料になっていることが多いんです。コピー用紙なんて呼ぶと味気ないですが、たとえば「ユーカリ紙」「アカシア紙」と言ってみると、途端に違って見えるじゃないですか。そういう身近な紙のことを、普段からもっとちゃんと見ていきたいなと思っています。よく「紙が好き」とか「紙のものが可愛い」と言うとき、コピー用紙みたいな白くてありふれた紙はその範疇外にあるんですよね。先日、ほぼ日さんと竹尾さん、デザインのひきだしで和紙の特集と展示企画をさせていただいたんですが、その中のトークイベントに出てくださったブックデザイナーの名久井直子さんは、幼い頃、クリスマスプレゼントに何が欲しい?って親に聞かれて、頼んだものがコピー用紙だったそうなんです。自由にお絵描きのできる紙が一包み欲しいって。 |
| 糸井 | 素晴らしいねえ。泣けてくる(笑)。そういう子どもが一人いると、人類史が豊かになりますよね。 |
| 津田 | 最後、今日ここにいない人の話になってしまいましたが、これは私の好きな話なんです。 |

