紙をめぐる話|紙について話そう。 No.28
|
既成の境界線を軽々と越えるデザインを、
次々と世に送り出しているおふたり。
その頭の中を少しだけのぞける対談です。
越境者ゆえの三澤さんの悩みに
山中先生が答えるウェブ版も必読です。
2019年2月19日
初出:PAPER'S No.59 2019 夏号
※内容は初出時のまま掲載しています
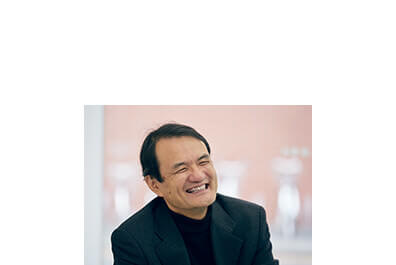
| 山中 | 「続々」展、拝見しました。ものから発生する不思議な現象を抽象化して、それを非常に繊細に、洗練されたかたちで展示台の上に再現していて驚きました。たとえば「動紙」では、磁石と遊びながら発見した動きを高い純度で滑らかに作品に落とし込んでいる感じが見ていてとても気持ち良かった。思わずツイッターに「久々に嫉妬を覚えた」なんて投稿してしまったくらい(笑)。 |
| 三澤 | ありがとうございます(笑)。今回の展覧会は、ただ過去の制作物を並べるのではなくて、展示物を展覧会後に続々と変化させていくという意思表示を展示しようと考えました。展覧会に答えがあるのではなく、その先を見据えるという意味では、山中先生がされている「研究」に近いのではと思っています。 |
| 山中 | ああ、だから共感したのかもしれない。デザイナーって製品だったり書籍だったり、広告媒体だったり、アウトプットを披露する場所は常にありますよね。それなのに僕らが展覧会を開くのは、東大の生産技術研究所で最先端の研究に取り組んでいる先生たちと一緒になって「未来がどうなるかは分からないけど、今こんなことができちゃうんですよ」っていうプロセスを見せることで、インスピレーションそのものを伝えたいからなんです。それが思わぬ人を巻き込んだり、フィードバックを受けたり、様々なコミュニケーションの中で大きく育っていったりすることを願っている。その辺りは似ていますね。 |
| 三澤 | そういった研究って、一度の人生で完結すると思いますか? |
| 山中 | 間違いなく終わらないですね(笑)。たとえば名作椅子のようなデザインはそれでひとつの終着点に至っていて、その後もずっと残ってほしいなんて思うわけですが、僕らがやっているのは途中でアイデアをぶちまけて「おもしろいでしょう?」と問いかけること。続きは誰かがつくってくれるだろうと。 |
| 三澤 | 私も、自分のアイデアを他の人が発展させても構わないと思っています。最近は特にかたちに対する欲求がなくなってきていて、見る人が反応するための余白のようなものをデザインすることに興味が向いているんです。 |
| 山中 | なるほど、だからかなあ、「続々」展を見て三澤さんはサイエンティストだなと思ったんですよ。現象のエレメントみたいなものを探し出して、台の上にそっと差し出す。それが何の役に立つのかは語らずに、「これをきっかけに何か考えてみませんか」と問いかけているような感じ。 |

いちばんおいしいところで止める。
| 三澤 | 確かにそうかもしれません。ただ、もしかすると、その先につまらないものしか待っていない可能性もあるんです。だから寸止めというか、「ここがいちばんおいしいところ」と感じるポイントを見極めることを大事にしています。 |
| 山中 | すごくよく分かります。どんどん駄目になっていく方向と、どんどん良くなっていく方向があって、どこかでそれがクロスするんですよね。がんばるほどつまらなくなると気づいた時点で「ここで止めちゃおう」みたいなね。 |
| 三澤 |
「動紙」は、紙という身近な素材が、何でもないかたちをしているから動きだけが見えてくるんですけど、あれが具体的な形状や質感をしていると…
|
| 山中 | たとえば鳥そっくりだったらつまらないよね。 |
| 三澤 | そうなんです。鳥のまんまのかたちをしていたら見る人は実際の鳥との違いを比較する視点にしかならない。意味付けのないかたちに留めておくことで動きそのものに注目が集まる。そういうところのコントロールを常に考えている部分は、山中先生の研究と通じているのかもしれません。 |
| 山中 | そうかもしれないですね。僕らがつくっているプロトタイプも、エレメントとしてギリギリ生きものの動きができる構造を追求していて、それ以上は無意味に生きものに似せない方がいいと思っていますから。 |
| 三澤 | 生きものではなくて、生きものらしさの入り口をつくりたいという感じでしょうか。「動紙」のある作品では健気さを感じさせる動きを目指したのですが、懸命に動いている紙に「がんばれ!」って声を掛けてくれる人がいたりして、とてもうれしかったですね。 |
| 山中 | それをやりすぎてしまうのがロボットの研究者たちだったりします。「不気味の谷現象」なんて有名な言葉もありますが、本物そっくりにしようとしてその直前までにしか至らず、見る人に嫌悪感を抱かせてしまったりする。一方で必ずしもアーティストは本物に似せようとしない。彫刻でも絵画でもそうですが、本物のずっと手前に、抽象化によってリアルに感じさせるポイントがあることを本能的に知っている。僕らデザイナーにとっても、いちばんリアルに感じるのは「これは鳥だね」って言葉で言われない範囲だったりしますよね。 |

紙だから。ふにゃふにゃだから。
| 三澤 | 先生はスケッチをたくさん描かれますよね。以前拝見したとき、凸凹している紙に描かれていたのが意外でした。 |
| 山中 | ちゃんと精製されていなくて滲んでしまうような紙が好きですね。キッチンペーパーなんかも絵がびろびろに滲んで楽しい(笑)。僕にとってスケッチは、自分の思考やものの構造を抽象化して紙の上に定着させることで、考えを客観的に見つめ直したり、他者とコミュニケーションしたりするためのグラフィック言語ですね。言葉では抜け落ちてしまう微妙なニュアンスまで表現できると思っていて。 |
| 三澤 | 先生は文章も書かれますが、始めは絵から入るんですか? |
| 山中 | 最初は言葉かな。コンセプト文を書いてタイトルを付けたり、詩みたいなものから始めることもあります。そこからグラフィック言語に転換していく。 |
| 三澤 | 私はスケッチをポンチ絵って呼んでいて、ポンチ絵だとふにゃふにゃの絵でもいい気がしますが、グラフィック言語っていうと… |
| 山中 | ちゃんと描かないといけない感じがしますね(笑)。でも目的は同じ。 |
| 三澤 | 最近、自分の絵がどんどん溶けてきていて、スタッフにも伝わらないことがあります(笑)。私の場合、自分自身に伝えるために描くことも多いですね。 |
| 山中 | 分かります。思考を一回外に出して、もう一度入れ直す。 |
| 三澤 |
先生があえて絵が滲む紙を使うのもそうかもしれませんが、曖昧な部分があるからこそ思考が広がっていくことがありますし、誰かに見せたときに思わぬ反応が返ってきたりするんです。
|
| 山中 | ふにゃふにゃだから伝わることってありますからね。 |
| 三澤 | それによって離れていたアイデアがつながったり、頭の整理ができたり、紙を通して人の脳みそを借りている感じがします。 |
| 山中 | 他分野の研究者たちと共同でものをつくったり、展覧会を開いたりするのも、それが目的でもありますから。紙を媒介させることで膨んでいく可能性ってあるんだと思いますね。 |
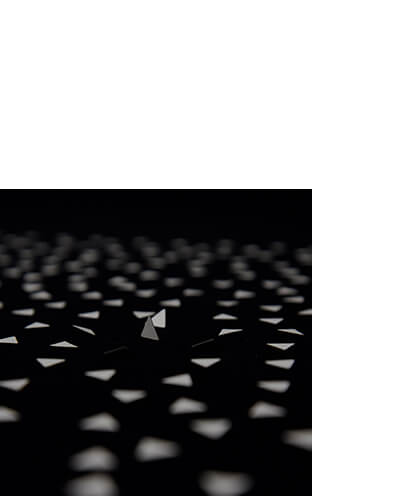
誰もいないところを歩く。
| 山中 | 三澤さんも僕も、科学者が技術を生み出して、それをエンジニアが設計して、デザイナーが外形を与えて、マーチャンダイジングして売り出すっていう20世紀型の産業構図にのらないものづくりをしていますよね。縦割りの垣根を越えて人が集まって、その場でつくってその場で発表しちゃう、みたいな。 |
| 三澤 | そうかもしれません。ただ、いつもそれを実現できているわけではないので、悩むこともあります。できることなら個展のように自分の思想のようなものを突き詰める活動だけをして生きていきたいのですが、実際にはそうもいかないことも多いんです。 |
| 山中 | いや、それは僕も同じですよ。論文を書けって大学に言われても困ってしまったり(笑)。最初にロボットをつくり始めたときにも、ただ働きしているような状態で、「これって仕事なのかな」と思っていましたし。でも、大丈夫。僕の経験から言うと、そっちの方がお金を生みます。従来のフレームから外れた好奇心で物事を始めると、普通ならデザイナーに仕事を発注しないような人が「そんな不思議なことができるんだったら一緒に仕事をしてみない?」って声を掛けてくれるようになって、少しずつ仕事がまわるようになります。まあ、10年後くらいに(笑)。だから何とかなるものですよ。 |
| 三澤 | なるほど…今のお話は、しばらく心の支えになりそうです。私はよく、「それはグラフィックじゃないよね、プロダクトでもないよね」ってカテゴリーで判断されることが多いんです。 |
| 山中 | 仕方がないから「アートだよね」とか言ってみたりしてね(笑)。そういうオリジナルなものってすぐには評価されたりマネタイズされたりしませんが、長期的に見ると大丈夫。しばらくは孤独ですけどね(笑)。 |
| 三澤 | 私と同じ年齢層の人たちみんなの心に響くお話のような気がします。はあ…山中先生も孤独だったんですね。 |
| 山中 | 誰もいないところを歩くっていうのは、そういうことですからね。 |
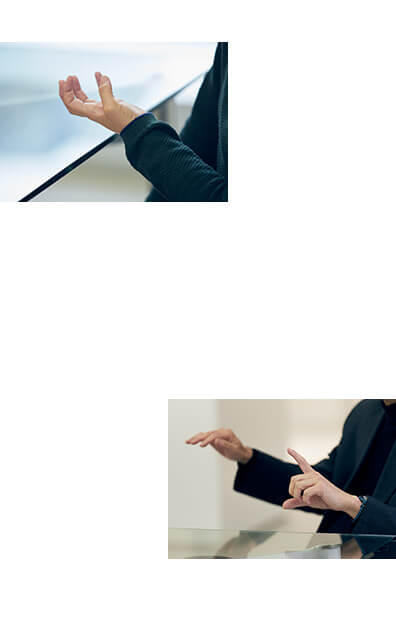
ワクワクできることに、素直であり続ける。
| 三澤 | 山中先生が私くらいの年齢のころ、どんなことを考えていましたか? |
| 山中 | 機械工学科にデザインの研究室をつくるからと声を掛けられて、東大に戻ったころですね。そのときの経験は宝物になっていて、そこで初めて「ああ、テクノロジーって宝の山だな」と気づくことができたんです。ただ、その後35歳くらいでフリーランスに戻ったときにはまったく仕事がなかった(笑)。共同事業者の妻と毎日漫画を描いて暮らしていましたね(笑)。半年くらい経って貯金も苦しくなってきて、そこから少しずつ、東大で見てきた新しいテクノロジーとデザインの関わりのようなことをベースに活動してみようと考え始めました。 |
| 三澤 | それからすぐに今のスタイルを確立されたんですか? |
| 山中 | 徐々にですね。ロボットをつくり始めて「変なことばっかりして、どこにいきたいの?」なんて言われながら、それなりに仕事としてまわるようになってきたのが40歳すぎくらい。その間は助走みたいなものだったかな。 |
| 三澤 | 40歳すぎ…私もがんばらないと。山中先生は、これからやってみたいことってありますか? |
| 山中 | 人を育てるのは案外おもしろいですね。「これやってみたら?」なんてけしかけるとポンッと花開く人がたまにいる。そういう瞬間は達成感がありますね。自分の経験を振り返ると、「おもしろそうな方向にとりあえずいってみるか」っていう軽さが大事だったなと感じているので、そういう風に動いてほしいなと思います。 |
| 三澤 | 最近でいうと、アーティストの荒牧悠さんも先生の教え子ですよね。 |
| 山中 | 彼女も学生のころから変なものばっかりつくっていましたね。本人も「私は一体何をつくっているんでしょうか」なんて言っていて(笑)。だから「とりあえず個展をやってみたら?」と助言したんです。それまでつくり散らしていたものを整理したり、テーマを与えたりすることで、やりたいことが分かるんじゃないかと思って。「わけのわからないことをし続けていいんですよ」という後押しをしてあげたかったんですね。 |
| 三澤 | 以前、永井一正先生にお話をうかがったとき、展覧会を「脱皮して生まれ変わる場」と表現されていたのが印象的でした。展覧会を通して自分を壊して、人の固定観念も壊して、その先に未来が待っていると。「だから90歳を過ぎても楽しいんだよ」と仰っていました。展覧会って人によって全然違う角度から臨んでいるんだなあと。 |
| 山中 | 空間を丸ごと自分でコントロールする個展の場合は特にそうですよね。つくってきたものを漠然と並べるだけでは伝わらないものがあるから、悩みながら足したり引いたりしていって、その過程で自分が求めている方向性がくっきりしてくる。三澤さんの「続々」展のようにね。 |
| 三澤 | 確かにそうでした。今回、山中先生とお話させていただいて、自分がワクワクできることに素直であり続ける人生でありたいと、心から思えるようになった気がします。 |
| 山中 | ええ、そうしてください…いやあ、楽しそうだなあ。 |

